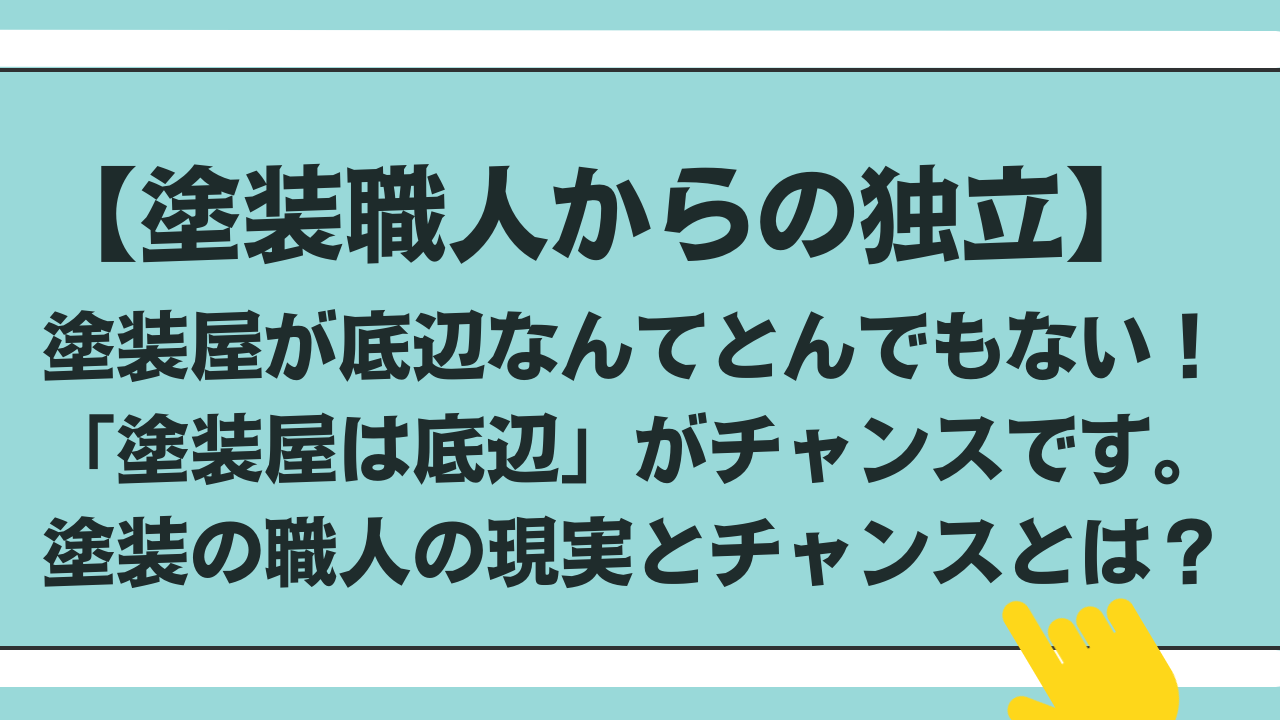あなたは塗装屋にどんな「イメージ」を持っていますか?
私は正直良く無かったです。毎日ペンキだらけでドロドロになって、くさい臭いを嗅ぐときも良くあります。でもそれはあくまでも「イメージ」です。
そんな仕事でもたくさんの魅力があるのです。
それは「独立」して初めて分かることでもあるのです。「経営」して初めて理解することです。
この記事を読むことで、あなたは塗装屋で「独立」する意味が理解できるでしょう。
そして今まで知らなかった塗装屋の「経営」を理解すると、他の塗装屋とは違った成果を上げることが出来て、塗装屋は「底辺」だと思っている人を「尻目」に働いて「自由」に稼ぐことが出来るのです。
塗装屋は底辺なのか?世間から見られるイメージと実態
・塗装屋の世間のイメージと実態の違いを解説
グーグルで塗装屋の検索をすると、関連キーワードで「塗装屋 頭おかしい」などのキーワードが出てきます。
このように「塗装屋が底辺」イメージを持たれることはよくありました。特に私が若い頃これを感じていたのです。なぜそう思ったのかをお話します。
私自身15歳から塗装の職人として働き始めて思ったのが、とにかく「汚れる」仕事、「匂い」がキツイ仕事、「危険」な仕事だと思ったのです。
でもこれは段々普通のことになっていきます。
一般的に塗装屋の仕事中の姿を見ると、とにかく「ドロドロ」でペンキ塗れ、それだけならともかく、「ホコリ」で真っ黒の時も良くありました。作業服だけではなく「頭から足」まで全身です。自分でも恥ずかしかったくらいです。
それくらい「汚れる」仕事でした。でもこれは若くて何も出来ない見習いだったからです。職人さんになればそんなことはありませんでした。
その頃はとにかく「臭い」のキツイ塗料が多かったです。「臭い」が緩い塗料が少なかったこともあり、「塗装屋」=「臭い」という印象はあったと思います。私自身も塗装屋を始めたときは臭いに強い印象を持ちました。
今考えるといつも「過酷」な環境で働いていたのだと思います。仕事に行って材料置き場に行けば、現場に出ればいつもこの「臭い」がついてきます。
作業中も「臭い」の強い塗料を塗っていると、「シンナー」に「酔っている」ことも良くありました。気がつけば時間が経過しているといったこともあったのです。
「塗装屋」=「臭い」というイメージがついたのはこのときで、当然毎日のように塗料の刺「激臭」を吸っているので良いはずはありません。
「塗装屋」=「頭おかしい」などのキーワードが出てくるのも理解ができるのです。そしてこんなイメージが定着して、塗装屋の職人が何かをすると、やっぱり塗装屋で「シンナー」を吸っているから、、、
こんな話になってしまうようです。
私が塗装屋を始めた40年前の話ならともかく、現在ではこの「過酷な環境」も急激に変化してきているのです。
新しい塗料はどんどん開発され、「臭い」のキツイ塗料もなくなっていき、環境が変化しました。以前から塗装屋で仕事をしている私たちからすると、ものすごい勢いで変化したと思います。
いまでは「強烈」な「刺激臭」がする塗料は極わずか、これはやはりエコを考えたとき全てのことが見直されたのです。
そして今では「臭い」がしない塗料を使っていても、道行く人は鼻を塞いで「シンナー」の「臭い」がするね、そういって通っていくのです。
「塗装屋」=「シンナー」を扱う仕事だと思っている人は、未だにこういう「イメージ」を持っているのです。実際にはもう「刺激臭」を放つことはそれほどなく、「強烈」な「臭い」のシンナーを扱うことも少ないのにです。
塗装屋が底辺というレッテルを貼られる理由
・塗装屋が底辺というレッテルを貼られる理由を解説
塗装屋が底辺」に見られる「原因」のひとつ、「臭い」の話の他にもあるのです。
汚れるということです。普通一般的に汚れるのは嫌だと思います。でも塗装屋をしているとこれが普通になってくるのです。多少ペンキがついていても気にならなくなり始めます、職業病なのかもしれません。
でもペンキがついていても良いのは自分の「テリトリー」だけです。車、作業着、道具くらいでしょうか?それ以外のところにペンキが付くことには敏感なのです。
塗装屋は綺麗にすることを目的にしているので、自分のものが多少汚れるよりも建物が綺麗になればいい。そのために仕事をしているのです。
だから自分のことはさておき、綺麗になるのであれば、作業着や車に多少ペンキが付いてもいいくらいに思っています。
だからペンキが付いて汚れている=汚い=だらしないと思われているのかもしれません。
ほかにも塗装屋で働こうと思えば、誰でも雇ってくれる「イメージ」があるからです。明日から塗装屋で働こうと思えば、雇ってくれるそんな「イメージ」があるからです。
「学歴」が必要ないからかもしれません。何も無くても身体動けば仕事が出来るから、そこから誰でも出来る、「バカ」でも出来るような印象を持たれるのかもしれません。
実際にどうでしょう?こう思って働きに来る人も多いのかもしれませんが、働きに来てまず感じるのは、思った以上に「ハード」だということです。
朝から夕方まで1日中、足場を上がったり降りたりを繰り返す日もあったり、ジッと1点を見てペンキを塗る作業をすることも、様々なことをするので仕事をした人の多くが塗装屋の「イメージ」を「破壊」されて帰ってきます。
これは建築の他の業種にも言えることだと思うのです。簡単そうに見えてもいざやってみると難しい。
塗装の作業を知っている人からは良く言われます。養生が仕事だね!これさえ終わってしまえば簡単に塗れそうな気はするけど、ところがそんなに簡単には出来ないですね。
私も思うんです。現場で他の業者さんの仕事を見ていれば簡単そうに見えるんです。ところがいざやってみると、これどうだったかな?わからないことだらけ、それと同じなんです。
ほかのテレビのニュースを見ていると、犯人の職業を見ると「建築作業員」とか「塗装業」とか出てくるわけです(笑)これには「正直幻滅」するのです。あーまたかって!
「建設作業員」の多くは「日雇い労働者」、このような印象です。ほかにも建築の職人をしていると「建築労働者」=「日雇い労働者」という「印象」があると思うんです。
でもこれは正直当たっているのです。職人の給料を見てみると「月給」ではなく、「日給月給」という1日労働をした合計日数分を給料日に受け取る。このような方式が取られているところが多いからです。
数年前から実施されている「働き方改革」なるもので大きく変化し始めたのが、「労働者」をある一定数雇う事業所は必ず社会保険を適用しなさい。これは当然のことなのですが、建築関係の事業所ではこれまでなかなか行われてこなかったのです。
これが見直されてきたことで、「社会保険」=「正社員化」が進みました。これによって月給化が進んだのかもしれません。でも多くの建築職人の給料体系を見ると未だに日給を取り入れているところが多くあります。
「建築職人」=「日給」=「日雇い労働者」のイメージがあるのです。建築の職人をしていると、これを感じる時があるのです。
どちらにしても、これは単なる「イメージ」、一部の人が抱いたことが「イメージ化」しただけでしかないでしょう。
塗装屋にもいろんな仕事がある
・塗装屋と一言でいってもいろんな業種に分かれます。
えー!塗装屋って塗装屋だろ?
そうではありません。イメージではツナギを着てペンキをペタペタ塗っているイメージがあるのです。同じように「塗装屋は底辺」だとイメージしている人もいるでしょう。
この「イメージ」は私が塗装屋の職人を始める時持っていた「イメージ」なのです。よくあるツナギを着て刷毛でペンキを塗る。
私は塗装屋をこうイメージをしていたので、働き始めてビックリします。毎日毎日「掃除」ばっかり、開けても暮れても「掃除」、「掃除」も「蜘蛛の巣払い」から「サビ落とし」、「ホコリ落とし」、「パテ研ぎ」、「塗料剥離」、こう書くとどんな印象があるでしょう?
「蜘蛛の巣払い」だと、「蜘蛛の巣」を取るだけですよね?ところがそんなに小さな「蜘蛛の巣」ではなく大きな天井一面に張り付いた「蜘蛛の巣」を払うのです。当然手や小さなものでは追いつきません。
「ホウキ」を使って払うのです。「イメージ」してみると想像がつきますよね?イメージした仕事とは違ったので「愕然」としたのを覚えています。
これは私が何も出来なくて見習いだったからです。
建物を塗装するだけでも大きく分かれているのです。大きな「ビル」や「マンション」、仕事は同じでやることも同じです。でもどうでしょう?
「鉄塔」とか「橋梁」とかこれらを塗装するのも塗装屋です。
小さな仕事をしている業者が、突然大きな現場の仕事が出来るかと言えば、そんなんことはありません。一人で仕事を行っている職人が、明日から10人20人集めて仕事をすることは難しいです。
逆も同じで、大きな現場で仕事をしている職人が、小さな現場で仕事をすることはできないのではないでしょうか?
大きな現場にはあって小さな現場にはない、大きな現場には無くて、小さな現場にだけあるもの。こんなことはたくさんあると思うのです。
ほかにも外装を行っている職人が内装の仕事を行う。ここにも違いがあるのです。
他にも塗装屋と言えば、「板金塗装」、車の塗装です。塗料から道具まで、全て違ってやることも全然違ってくるのです。
塗装屋と一言でいっても、他にもたくさんあるのです。
独立塗装屋になって成功するために必要なこと
・独立塗装屋になって成功するための解決策を解説
「独立塗装屋」とは、自分で事業を起こすことです。いわゆる「起業」です。起業と言えばどんなイメージでしょう?
会社を興して仕事をする、社員を雇って仕事をして規模を拡大して安定的な企業を目指す。社会に貢献する。こんなイメージでしょうか?
でも塗装屋で独立しても、はじめはどこかの仕事をもらう。同じような仕事をしている同業者、又は建築工事に携わっている業者、要は建築関係の仕事に関わっている業者から仕事をもらって仕事をするのです。
一度仕事をもらえれば、次も塗装の仕事があればもらえるでしょう。
仕事をもらう相手によって行うことが変わってくるのです。仕事自体が変わるわけではありません。事業形態が変わるのです。
元請け、下請け、孫請け・・・・・・
このように仕事を請けるというのですが、どこで請けるかによっていろいろ変わる。元請けなら仕事を探して来なくてはならない。
「下請け」「孫請け」・・・・なら仕事が来るまで待っているしかない、、、?
ここも「塗装屋が底辺」と言われる所以かもしれません。
どこで仕事をもらおうとも、とにかく「塗装屋で成功」するには「利益」を上げなくては始まらない。独立しても仕事をたくさん熟していても「利益」が上がらないとどうなるのかというと?
「倒産」です。
そ・そ・そんな!
でもこれは事実です。
オレは仕事をして「利益」を得ている!本当でしょうか?
あなたが「利益」だと思っているものは、「手間」じゃない?仕事をして受け取っているお金、「生活費」じゃない?
「利益」とは「生活費」ではなく、仕事をして得たお金の中から、「経費」や「生活費」を差し引いた残りのことなのです。
100万円分の仕事をして経費を50万円支払って、30万円で生活した残り、20万円が「利益」だということです。
この「利益」を積み重ねる、ただ積み重ねるだけではないのです。ここに工夫をすることでより多くの「利益」を得ることが出来るのです。
成功するには?
あなたが望む「成功」によって行うことが違うのです。
「成功」、考えてみるといいでしょう!
塗装屋で食べていくために気をつけるべきこと
・塗装屋で食べていくための注意点を解説
塗装屋で食べていくのであれば、塗装の職人をしていればいいのではないか?塗装の職人としてどこかに所属していれば、勝手に仕事を段取りしてくれて指示を出してくれるからです。
こんなに楽なことはありません。
塗装屋で独立して一番「苦労」するところがここだからです。いつどこで何をしていても気になること、それが明日の仕事。
明日の仕事も気になるのですが、本音を言うと将来の仕事です。常に仕事を続けて行けるのかどうか?
来週や来月、はたまた来年は?こういうことです。
そんなことわかるか!!!
こう思うでしょ?
それこそ全くわからない。雲をつかむような話です。そんなこと考えても仕方がないでしょ?
でも事実です。
独立して現状忙しくて仕事に追われていても、いつ仕事が途切れるかはわからないのです。これが一番不安な部分だからです。「塗装屋が底辺」と思われる、「建築業界全体」かもしれません。
だから塗装屋で食べていくだけであれば、独立しないで勤めて仕事をすることをおススメします。
でもその代わり、仕事で成功することはあり得ない。どこかの誰かの「夢」があなたの「夢」と同じで一緒にその「夢」を「叶えること」が出来るのならば、一緒に仕事も出来るでしょう!
とにかく目指すところが、塗装屋で食べていくことを求めているのなら、独立する必要はありません。
お勤め一択です。
良い塗装屋を探して仕事をするといいでしょう!
塗装屋専門コンサルの視点から見た塗装業界の将来性
・塗装業界の将来性を解説
「塗装業界」を40数年前から見てきた私が考える、「塗装業界」の「将来性」
どのような未来を描いていくのか?
現状、塗装店は塗装の元請けでたくさんの仕事を生み出しています。
もう「塗装屋を底辺」なんて言わせない!(笑)
でも塗装の仕事をする人の数は減少しているでしょう。
これからも今までと同じように業界を盛り上げていくには、どのようにすればいいのか?
これはどの業界においても常に言われていることで、特に「建築」、「リフォーム市場」においてはまだまだ「人材」が足りていない。「人材」を育てる必要があると思うのです。
現状を見ても、一時の「不況」でたくさんの建築職人さんが「廃業」、「転職」されて行ってから職人の数は増えていません。ちょっと忙しく成ればたちまち「人手」が無くなります。
これでは正直仕事になんてならないでしょう!
どの業界も常に「問題」を抱えてきて、それをクリヤーし進歩してきました。いつも何かの壁にぶち当たるときがくる。このときどのようにするのかによって「将来」が生きてくる。
今何をするべきなのか?
根っこを掘り起こせば、それこそとんでも無いことを「想像」してしまうのですが、このとんでもないことをすることで「変化」を起こすことが出来る。
ホントの意味で必要なこと。
それは「夢」を見ることです。
みんながみんな「夢」を見る(笑)
バカ言ってんじゃないよ!
こんな声が聞こえます!
でも真剣なんです。
夢を見なければ、何も始まらない!
誰かが大きな「夢」を描いたから、現状存在することがたくさんある。
この先へ進むとどこへ行くのだろう?ただ素朴にそう思った人が進んでいって新しいところへ辿り着いた。
歩いていて、飛んでいけたらいいのに!と思って作ったものが、今では当たり前に乗っている「飛行機」。
会いたいな!でもすぐには会えない。会っているように話せたらいいのに!?で生まれたのが「電話」。
今では無料で通話できたりする。
それこそ30年前なんて、「携帯電話」を持っている人が少なかったです。私が始めて「携帯電話「を持ったとき、仕事で必要なのでもったまで、本当はだいぶ格好を考えてですが、、、
30年で大きく変わりました。
このような「変化」が起こるのです。
「夢」を描けばもっと早く、もっと凄いことが
「塗装業界」ももっと進化してい行くでしょう!
私が思い描いていること、それは全ての人(職人が)自由に仕事をする世界です。
自分で考えて、自分の仕事を創り出して行う。個人事業主がたくさん増えること。仕事の心配をすることなく自由に働ける環境を自分自身で築いていける。こんな世界を「イメージ」しています。
一人が二人、二人が三人。
たくさんの人が手を繋げば大きなことが出来る。
「チャレンジャー」で大きなことが出来る。更に行動できる人はますます大きなところへ向かって言って欲しいです。
小さく成功したい人も大きく「成功」したい人も同じように「成功」する「未来」を築く。
全ての人が「自由」に「表現」する。
「塗装業界」だけの話ではありません。
私が考えるのは「塗装業界」なので、「塗装業界」の人が更に「成功」を収めることを出来る世界を創ることです。
まとめ
・塗装屋は底辺なのか?
私が知っている塗装屋について話してきました。でも「塗装業界」は大きく変わりました。
以前は独立しても、どこかの建築業者から仕事をもらって仕事をする。塗装屋は家を建てるときの一部の仕事を担う業者のひとつでした。
あるとき聞かれたことがあります。
塗装屋の仕事が建築締める割合はどれくらいですか
これを聞いて来たのは「基礎工事業者」でした。そのときはどういうことかと思ったのです。よく分からなくてピンとこなかったのですが
家を建てる際、「基礎工事」が占める割合が10%とか20%忘れましたが(笑)「基礎工事」は家を建てる際、大きな割合を占めているのだと痛かったようです。
それに比べて塗装屋はと言えば、数%それもごく少ない割合でした。確かにそれほど比重は多くない。家を建てる際見積もりをしても、全体の金額からすると、ごくわずかな金額にしかならないのです。
その塗装屋が、今では「リフォーム市場」の主役です!嬉しいじゃないですか!自分たちがずっと関り続けてきた業種、「底辺」なんて言われながら「リフォーム市場」で活躍することが出来るなんて
それも「元請け」として「お客さん」と直接関わっているのです。「夢」のような話です。
これはみんなが願ってきたから、塗装の職人から独立して上手くいかなかったから、辿りつけたのだと思うのです。
いやー素晴らしい!
これからも大きな「夢」を描いて行きましょう!
いかがだったでしょうか?
私も塗装の職人から独立して、「夢」なんて考えたこともありません。それどころか、仕事をするのに必死、お金をを得るために
私が独立して仕事を本気で意識し始めたのは、直接お客さんから仕事をもらうようになってからです。
自分が一生懸命に仕事をすれば、お客さんが飛び上がるように喜んでくれたことです。そこで更に自分の仕事に磨きをかけることが出来たのです。
もし、私が以前のまま「孫請け」の仕事をしていたら、ここまで仕事を「意識」することはなかったでしょう。
それこそ今書いているような経験はできなかったのです。あのとき仕事のことを「意識」したことで、より一層仕事に力が入っていったと思うのです。それくらい重要なイメージ、行動を起こすことです。
そんな私が、塗装の職人から独立して、十数年経ってから自分のお店を軌道に乗せて、今ではこんなことを言いながら、「自由」に過ごさせてもらっています。
あなたには私がしたような遠回りをして欲しくないのです。
だからこの文章を書いています。
この文章があなたの独立後の事業経営に少しでもお役に立てれば嬉しいです。